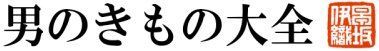「染人 橋村重彦 展」 2002/11/08
2002年11月の休日に京都を訪れた際、パールトーンの國松社長のお誘いで、
彼の知人である友禅作家の方の展示会を見学させていただきました。
橋村氏ご本人とお会いして、いろいろなお話を伺うことができました。
友禅創始期の技と表現に挑む
- 洛北・花脊友禅染 -
染人 橋村重彦 展
主催/橋村重彦 染色美術研究所
後援/京都新聞社・(財)平安建都1200年記念協会
毎日新聞京都支局・日本繊維新聞社
協賛/花脊 白眉庵
京都文化博物館
展示会のあった場所は、京都文化博物館の別館で、
ここは旧日本銀行京都支店(現在は重要文化財)だった建物だそうです。
ちなみに本館は近代的な7階建ての建物で様々なジャンルの展覧会などが開かれています。
後の建物が京都文化博物館の別館。
京都府 京都文化博物館
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/bunpaku/
橋村重彦さんとその作品
実はこの展示会、写真撮影完全禁止だったのですが、國松社長の強引なお願いで
撮影とホームページでの紹介を主催者ご本人より許可していただきました。
掲載写真はほんの一部であり、作品の解説や染色技術のお話を述べることはできませんが、
どうせやるならとことん追求したいという姿勢で取り組まれた作品群ばかりで、
見るものを圧倒しますが、興味のある全ての人がじっくり見れないのは残念かも。
(この展示会に足を運んだ人だけしかそれを確認できないという意味で)
橋村さんの真後ろは「懐郷」と題された立浪菊花文様の作品。
展示会で配布されるポストカードにも使用されていました。
展示会を閉鎖的にする要因
どんな職人技を繰り出して創出された作品も、大勢の人に見てもらってこそ価値が高まるはず。
橋村さんだけでなく、多くの作家さんやオリジナル商品を開発している人たちが、
こうした作品を完全にOPEN化できないのは、同業者の中で心無い人たちが、
こうしたデザインや意匠のコピー商品を瞬く間に作り出してしまうからとのことで、
そうした問題に対する自己防衛の意味で、作品の披露が閉鎖的になりがちというのです。
違法コピーに対する抵抗の手段が、秘密裏的な展示会とせざるを得ないという現状は、
おそらく作者の想いとは反するはずであり、非常に残念なことのひとつです。
なぜなら、大勢に見てもらいたいからこそ、展示会は開催されるものなのですから。
これらの問題を完全にクリアすることは他業種においても困難な課題ですが、
オリジナルであることの証明を他の手段と併用して行うことも必要でしょう。
たとえば、製品全てに消えないシリアル№をつけるとか、違法コピーされた時の対応を
業界全体で確立するなど、課題と向き合ってひとつひとつクリアして欲しいと思います。
すばらしい作品こそ、一人でも多くの人の目に触れるものであって欲しいもの。
そしてより多くのユーザの意見を取り入れることで、作品とは異なるコンシューマ商品も
同じ技術の中から創出されるものであって欲しいと願っています。
「親子4人全員が染のエキスパート」
橋村さんの作品はどれもこだわり抜いた逸品ばかり。
現役で親子全員が染色の技を磨く職人さんだそうで、
これは業界内でも珍しい存在ではないでしょうか。
それぞれの息子さんが個性を生かした役割を受け持ち、
すばらしい技術を世に披露されています。
これからもぜひ頑張り抜いて欲しいと願っています。
左からお父さんの橋村重彦さん(染人)、
長男の俊則さん(染人)、
三男の太輔(たいすけ)さん(絵師)、
次男の嘉晃(よしあき)さん(糊置師)
二枚目揃いの息子さんたちなので、彼ら自身をモデルに、
ぜひとも男物の展示会も企画して下さいね。
付近の散策スナップより
おまけ情報
京都文化博物館のすぐそばに、ちょっと怪しい和風雑貨のお店?を発見。
中には入らなかったのですが、店頭の男のきものディスプレイが気になる・・・。
で、近づいてみました。
↓
左胸のポップには「家に帰ったらきものでくつろごう!」と書いてあり、提案は実に正しい!?
でも、このままだと、ゲージュツ家のアノ人みたいだし、万人向けではなさそうな・・・。
ちなみにきものの素材はジーンズで、首にスカーフ?、柄足袋にサンダルを履いてます。
和風なテイストも感じ方は十人十色ですから、こんな楽しい提案もOKですけどね。